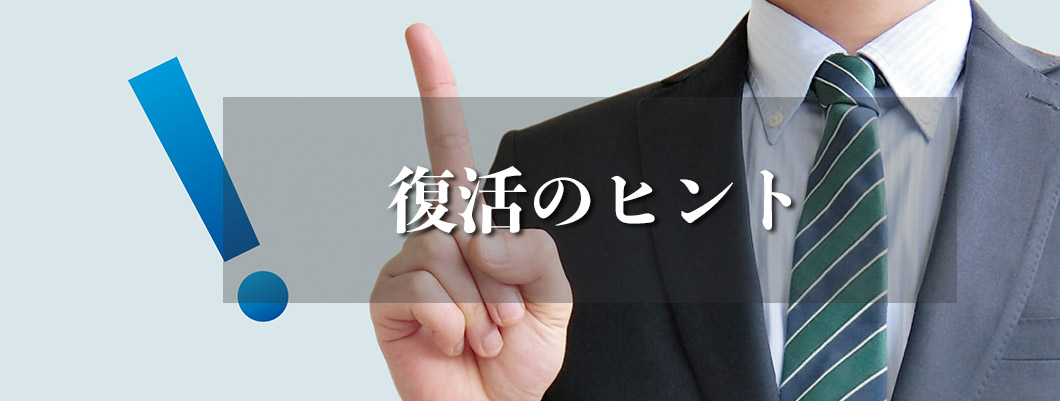
若い人来たれ
{ }
復活ノート
「若い人来たれ」
この不況で、都会で勉強する子供への仕送りが減っているそうですね。
20何年ぶりに8万円を割ったとか報道されていますが、こんな平均値は、どら息子やどら娘が、親に、値上げ交渉するために使うぐらいで、何の意味もありません。
余裕のある親なら、50万ぐらい送っていますし、余裕のない親は、子供のほうから、仕送りを断って、奨学金やバイトで大学生活を送っています。
私も、昭和40何年かに、京都で大学生活を送りましたが、仕送りは1万円でした。
当時は、そんなに低いほうではなかったと思います。何しろ、家賃も3畳のアパートで3000円ぐらいでしたし、風呂屋も30円ほどだったのですから。
もちろん、バイトをしましたが、京都の場合は、いざとなれば旅館に駆けこめばいいのです(寝食は無料で、特に修学旅行シーズンはくたくたになるので、お金を使うこともないのですから)。
そういうわけで、勉強のことはさておき、あのくらい飲んだときはなかったというのが印象です。
バイトは、庶民の子供ならば生活の一部です。そして、女子のほうが実入りはいいはずです(その結果、卒業しても、キャバクラ嬢にあこがれる女子大生が多いのは考えものですが)。
感謝をしていいはずなのに、元のバイト先をあしざまに言う若者が多いのはなぜでしょう。
私が活動をしている地域に有名なステーキ屋がありますが(今は全国的に名前が知られています)、かつてそこでバイトをしていた若者が、「あそこには行かないほうがいいですよ。
昼定食も、他なら800円ぐらいのものですし、焼くのも、新入りのバイトです。
にんにくのスライスも、市販のものを水で戻しているだけです。最初に出てくる生ハムもお代わり自由なのに、わざと言わないのです」と教えてくれました。
これが、バイトでも、バイト長としてどこかの店を任されていたのなら、こういうことにはならなかったのでしょうか。
正社員でも、「私の親は、ここへは絶対入れない」と、自分の職場である介護施設について話すスタッフもいます。
職場は、逆から言えば、社員と(バイト、正社員にかかわらず)、経営者や上司、同僚との関係でできています。
しかし、バイトは置きざりにされがちなので、いつまでもネガティブキャンペーンをする人がいるのでしょう。
つまり、仕事に対する意欲はあったのに、受けいれられなかった思いのあらわれかもしれません。
私自身は、役務(えきむ)ビジネスはこりごりですが、そういう若い人を集めて、人件費を下げたい、あるいは、人が育たないと思っている企業に入りこむビジネスはどうですか。
以前から言っている「新しい便利屋」も、「新聞配達の請けおい」もおもしろいと思います。
すべての労働集約的な企業に目をつけましょう。郵便配達も取れるかもしれません。
組織も、若い社員に作らせたらいいのです。
みんないきいきと働いてくれるでしょう。仕事も、人生も、自分の計画どおりにいくことほど幸福なことはないのですから。
