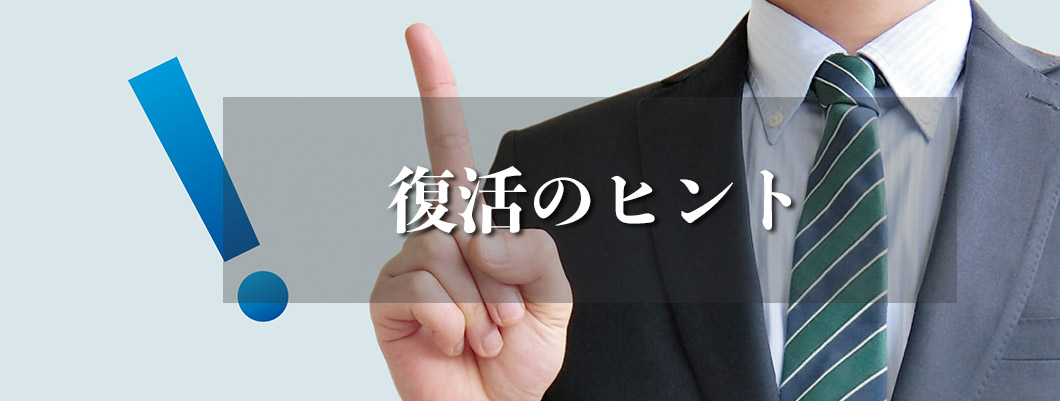
屋台村
{ }
復活ノート
「屋台村」
先日、叔母が、「回転ずし」に行きたいというものですから、近所の店に向いました。
ところが店には200人以上が待っている状態でした。ほとんどが子供連れのようでした。
仕方なしに、いつものレストランに行くことになりました。
日曜日の午後6時ごろで、「父の日」というのが悪かったようです。
私が知っている人は、どうしてもファミレスに行く場合は、中学生と小学生の娘二人に、まず家でおにぎりを食べさせる作戦を取っていると言っていましたが、高いファミレスから、「回転ずし」にシフトしているのを目の当たりにした次第です。
不況であっても、「ハレの日は外で食事」いうのが生きているようです。
ところで、台湾やベトナムの屋台は有名です。夜、そういうところに行けば、ものすごい人が屋台でごはんを食べています。
聞くところによれば、東南アジアの庶民の家庭にはもともと台所がないので、三食とも「外食」となるのです。
以前、部下を連れて、横浜の中華街に行ったことがあります。
「ほんとのおいしいものは裏通りにある」と通(つう)ぶって、狭く暗い横道をあちこち歩きました。
すると、玄関は真っ暗なのに、7,8人の人が楽しそうに食事をしているが見えました。
「ここに入ろうか」とドアを開けると、どうも様子がちがうようです。結局家族や親戚が晩ごはんを食べているところでした。
今は知りませんが、小さな中華料理の店は、午後8時頃に営業を終えて、あとはゆっくり食事を楽しもうということでした。「金儲けより、家族だんらんが大事」があるのかもしれません。
日本では、家で食事をするといっても、夫婦とも仕事で忙しく、冷凍のものを買ってきて、それを食べるということが多いです(お弁当もそうです)。
極言すれば、店へ行ったときの人件費を始末するだけで、食べているものは一緒ということかもしれません。
この際、東南アジアの人々のように、三食とも食べにくる屋台村を作ることはいかがですか(原則として、一月の平均食費を30で割って、そして3で割って、一皿の単価を決めていくのです)。
朝や昼はともかく、晩は家族、近所の人が楽しく食事や会話を楽しめる場所です。
もちろん、スーパーやコンビニのように、日本中同じ味ではなく、旬を大事にした料理を出してください。
これは、新しい食文化になりますよ。料理だけでなく、家族、地域を再生させることにもなります。
屋台村そのものは、以前はやったことがあります。しかし、東南アジアということにとらわれすぎて、ファミレスに敗れさったのです。
「回転ずし」も壊滅の歴史を持っています。今の隆盛は、ロボット職人が定着したからでしょう。
「ハレの日」の屋台ではなく、「ケの日(日常)」の屋台は待たれています。
