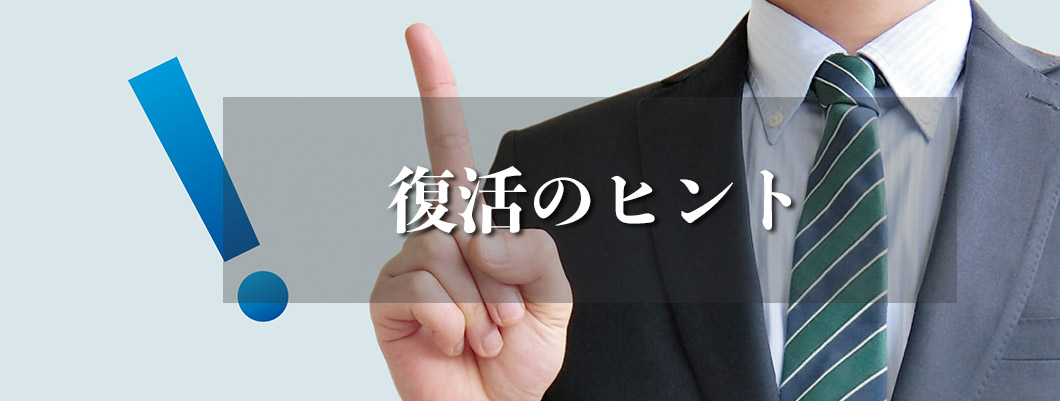
視点
{ }
復活ノート
「視点」
多才な松尾貴史は、昔から「キッチュ」という名前で物真似をしていますが、その代表的なのが藤本儀一の物真似です。
藤本の「こうしゃくたれ」の声色で、「まなぶという字は、まねぶから来ていましてね。つまり、まなぶことは、まねをすることからはじまるわけです」でに人気が出ました。
物真似はともかく、その語源の是非もともかく(正確には不明だそうです)、確かに新入社員は、数か月もすると、直属の先輩とそっくりの物の言い方をすることがあります(当の社員は、それを指摘されるまで気がつかないようです)。
私たちも物心がつくと、まず親や兄弟の真似をして人生をはじめるのです(もちろん、途中で、それに反発することもあります)。
仕事でも、訓練学校に行ったとしても、それで仕事をはじめることはできないので、どこかで、真似をするわけです(親の会社を継ぐ場合でも、まず別の会社に勤めることがほとんどです)。
私が、「今までなかったビジネス」とえらそうに言うときでも、経営方式そのものがはじめてというのではなく(それは、堅実な会社をおおいに真似をすべきです)、今まで誰も目をつけなったもの、あるいは、今まで当然と見なされていたもの、あまり評価されなかったものをビジネスの真ん中におくことと定義したほうがいいでしょう。
さて、日本の社会は、今や少子高齢化が土台となっているのは周知のとおりです。だから、政府も、民間もそれにそう沿う政策やビジネスが多いわけですが(どこもかしこも、シニアなんとかと言って、高齢層を取り込むのに必死です)、それに追随するだけでは、「今までなかったビジネス」はできません。
もう少し細かく見ると、高齢層を、大きなマーケットと見る場合と社会の変革を阻害する世代と見る場合があります(大阪の「都構想」の住民投票では高齢層が改革を阻んだとなっています。市長と府知事が原因なのに)。
今度は、別の視点から見ると、高齢者一人一人は個性のかたまりで誰とも似ていない存在です。
つまり、見栄っ張りでも、頑固でも、長い時間と、個人の精神的・肉体的事情や家庭の事情などが絡み合って、その人だけの見栄っ張り、頑固になっているのです。
そういう難しい層に入り込むビジネスはどうでしょう(それにつけこむのが、「振り込み詐欺」や悪徳商法です。彼らは、高齢者が孤立していることを知っているのです)。
そこを踏まえていえば、私が今興味あるのは、「スマホの相談サービス」です。
高齢層も、かなりの割合でスマホをもっています。しかし、私の知っているご婦人は、詳しい主人に聞くとうるさがられると言っています。さりとて、その都度キャリアの店にも行けないらしいです。私も聞かれたら答えていますが、どうも持て余しているようです。
高齢者一人一人の孤立をどう受け止めるかを発想の原点にすると、「今までなかったビジネス」ができます。
