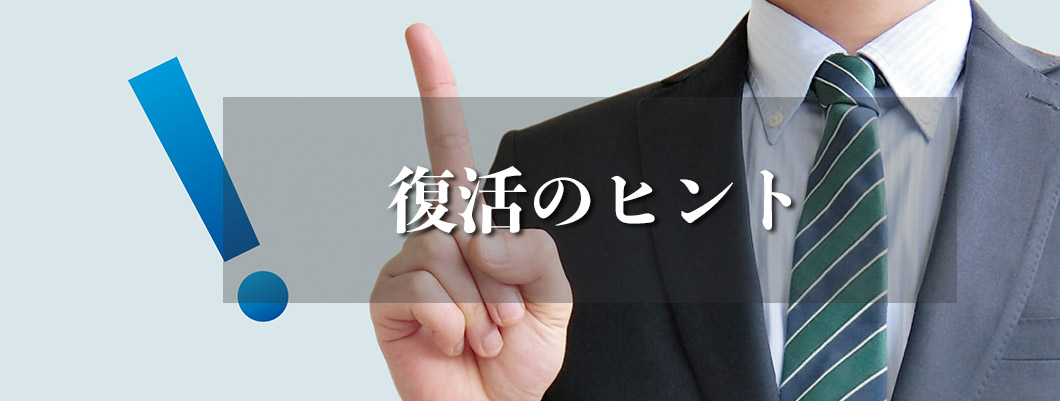
災害サービス
{ }
復活ノート
「災害サービス」
阪神淡路大震災から28年たちました。当日は堺市の自宅にいました。自宅は大阪湾から5キロ程度の距離ですが被害はありませんでした。
淡路島や神戸の被害は報道されているとおりすさまじいものでした(神戸支店があるので心配していましたが、神戸や淡路島のことは当日の午前中はあまり報道がなかったので被害はないものと考えていました。)。
大阪の中心部はあまり被害がありませんでしたが、堺から本社のあった天満橋に行くのに車で3,4時間かかりました(日頃は高速道路で30分ぐらいですが、当日は高速道路は渋滞で利用できませんでした)。
三宮にあった神戸支店に行こうにも行けず、数日後福知山線と神戸電鉄を使って三宮に行くことができました。
支店の入っているビルは無事でしたが、顧客が被害を受けているので、売り上げはなくってしまいました。
それが倒産のきっかけかもしれませんが、私の対応能力が欠けていたからです。
当時、関西人の頭には関東大震災のイメージがあってか、「関西には地震がない」と全員が思っていたように思います。
それで被害が大きくなった原因の一つかもしれませんが、木造住宅の補強があれば死亡者は少なくなっていたはずです(死亡の8割は頭の強打らしいです)。
その後、東日本大震災、熊本地震と続いていますが、どこも、「うちには大地震はない」と言えなくなってきました。
そして、南海トラフ地震です。ネットを見ると、「何年以内に何パーセントで起きる」という記事が山ほどあります(予想どおりなら私も死亡数に入っています)。
こういう事態になって、地震だけでなく、台風、大雨などの天変地異に対して、国や地方自治体も本腰を入れていますが、個人の生活までは目が届きません。
そこで、我らの出番です。まず、行政などの対策を調べて(避難先での段ボールベッドはスタンダードになってきましたが、そういう避難生活全般を含めて)、他にないか考えましょう。
そして、個人の生活です。何が不足するか、何があれば便利かに常にアンテナを張りめぐらせておくことです。
しかも、それは、緊急時だけでなく、日頃の日常生活でも利用されるはずです。
天変地異の直接の被害者だけでなく、関連死も含めて、多くの命を救うことになります。
私が以前考えたのは、災害はどこで起きるか分かりませんから、お互い住む場所を提供する「契約サービス」や、「大水で家が流されても水に浮く家」(これは今どこかのメーカーが研究しているそうです)などを提案しました。
誰か、社会のために挑戦しませんか。アドバイスします。
